令和ロマンが連覇を果たし、M1の歴史が塗り替えられたような今回。
今までもお笑いが好きというところからM1を見ることはありましたが、今年ほど熱量を高く見たことはありませんでした。
それは個人的にNON STYLEというコンビが好きで、その好きなNON STYELEも挑戦していたM1の2連覇を実際に達成してしまいそうな空気感が漂っていたということもあるし、少しずつ自分の中に蓄積してきた”M1の見方”というのを確認する作業として、2連覇という重さのある今大会がピッタリな気がしたから。
ということで、ここでは”審査員としてM1を見る”というような視点ではなく、審査員の方たちがどのように点数を付けているのか(なぜそのような結果になるのか)というところを理解しよう(M1というただでさえ面白いものを、自然に納得感あるものとして受け入れられるような視点を手に入れよう)という、あくまでも視聴者視点からの考察を深めていこうと思います。
前提:昔のM1は、審査内容と視聴者の声に乖離が多かった
自分の感覚の話で申し訳ないのですが、昔のM1は結構視聴者の声と審査内容に乖離が今以上にあったと思っています。
当然その審査や結果に納得している人も少なくはなかったですが、
「〇〇の方が面白かった」
「〇〇の方が好き」
「優勝したコンビの面白さが分からなかった」
という声をSNS上なんかで目にすることが昔はかなり多かったという感覚があって、自分も同じような感覚を持っていることが少なくなかったです。(どこの年の誰とは言いませんが、「この人が優勝?」「この人が落ちて、この人が上がるの?」という感想を持つことはかなりありました・・・)
またかつてM1が一時休止してTHE MANZAIが漫才の賞レースとしての代わりをしていたような時代には「国民ワラテン」なる視聴者票が、他の審査員と同様に1票分与えられていましたが、その国民ワラテン票を獲得したコンビが勝ち上がった割合は約44%(8/18)であり、その半分以上は視聴者と審査との乖離があるような結果となってたわけで、これではその審査に違和感を持ってしまうのもやむを得ないでしょう。
だけど、これだけ面白いものを見ているのに、その結末に違和感があるのってすごく勿体ない気がする。
結果に納得がいかなくてもその結果は揺るがないのだから、その結果になる理由を理解できるようになろう。
これが自分の”M1の見方”を育てていこうという出発点。
しかし最近ではそんな声も減ってきたような気も、正直しています。
これは審査員の入れ替わりや審査基準の調整からそうなっているのか、見ている側のお笑い観が育ったからなのかどうか、決定的なところは分かりませんが、そんなところも含めて考察をしていこうかなと。
M1の審査を考える
前提として、自分がある程度の熱量を持って見始めたM1が2016年からなので、それより前の話には言及していないものとしてください。
あくまでも、かなり近代のM1の話ということで。
そもそも一般人が漫才に点数を付ける仮定した時、その審査基準は人によって様々だとは思いますが、その軸になるのは”面白さ”であるはずです。
だって面白くないものに高得点なんて変な話ですから。
しかしこの”面白さ”を感じるところは人によって異なっていて、全てを一元的なものとして評価するのは不可能です。
だからこそ、お笑いにおいて結果を出してきた権威のある方たちが漫才を審査し、本来正確には付けれらない”面白さの優劣”を判断して点数をつけ、その点数を権威によって正当化する。
これがM1グランプリの視聴者からの見え方なんじゃないかと思います。
(当然芸人さんからすればそんな意識はなく”認められたい人たちから認めてもらう”という場でもあることは理解していますが、あくまでも視聴者から見た時には上記のようなものであるはず。)
そして、だからこそ、視聴者がただ見る漫才とプロならではの視点で見る漫才との間に乖離が生じてしまい、その審査結果に対しての納得感の無さが発生してしまうわけです。
だったら、視聴者がただ見る漫才でも審査の理屈さえ分かっていれば、納得はできずとも理解はできるはずというのが自分の考えです。
ということで、以下に自分が考えてきたM1の審査に関するロジックを述べていこうと思います。
審査員を見る
まず、M1の結果に対しての納得感を得るためには、その結果を生み出している審査員の方を理解しなくてはなりません。
かつてはこの審査員の方々に対しての芸人さん達の声で炎上的なこともありましたし、視聴者からも不満の声が上がって炎上していたりもしているわけですが、まずはそこを見ていきたいなと。
そして、毎年10組の人生を決めるような重大な決断を、上記のリスクに晒されながらもされてきた方たちには最大限の敬意を払っていることを予め言及しておきます。
審査員を見る意味
M1の審査員は、人数が増えたり減ったりしながらも、そう大きくは顔ぶれの変わることがありません。
審査員が9人に増えた2024年ですら、4人は前年でも審査員を勤められていた方、2人は過去に審査員経験のあるM1チャンピオンなので、完全新規の審査員は3人でした。
だからこそM1という大会の質が大きく変化することもなく続いていて、逆に言えばちゃんと理解していけば分かるもののはずなんです。
そんな審査員のジャッジの詳細を掘ることはその人自身を掘ることになるわけですが、そこまで詳しいわけでもないですし、考えすぎることが邪念になってしまっては問題なので、まず前提として大きく3タイプに分類することで分かりやすく考えます。
当然、はっきりと分かれているわけではなく、ある程度この傾向が強い気がする程度の分け方であることをご留意いただけますと幸いです。
審査員のタイプ ①漫才(師)のあり方重視
例:オール巨人さん、上沼恵美子さん、博多華丸・大吉の大吉さん、ノンスタ石田さん、アンタッチャブル柴田さん など
例えば、王道のしゃべくりや漫才をベースにコントをする漫才コントを重視し、コント要素の強いコント漫才うあどう分類すればいいか分からない漫才をやや減点する傾向のあった巨人さん。
和牛に対し、ステージ上での傲慢さが見えたと言及したような上沼恵美子さん。(その道を極めたような方から見れば、漫才やお笑いへの姿勢というのも見えてるんだろうという解釈です)
審査のテーマに”新しさ”や”ネタ時間”というのを織り込んでいることを審査コメントで言及していた大吉さん
2024年ではトム・ブラウンに対して、「お笑い感度の高い人達は面白い」と評価しながらもやや低い点を付けた石田さんや、「スタジオの空気感ほどテレビの前の人は笑っていないんじゃないか」とコメントしていた柴田さん、つまり誰に向けてのお笑いをするのかという姿勢も評価していた2人。
そういった、そもそも(M1においての)漫才というのはどういうもので、漫才師はどのように向き合っているのかというところを前提にしながらの審査、言い方を変えれば「M1というフォーマットの上に提出された漫才(師)という作品」としての評価をするタイプと考えるとしっくりくる感じ。
審査員のタイプ ②-①ウケ重視-自分型
例:立川志らくさん、ナイツ塙さん、海原ともこさん
ランジャタイに最高得点を付けた立川志らくさん。
2022ではヨネダ2000に、2024ではトム・ブラウンに最高得点を付けた塙さん。
2024の審査コメントとして「技術的なことは分からないから、一個一個見たい」と明言していた海原ともこさん。
分かりやすい例を上記に挙げましたが、これはシンプルに「自分が面白いと思ったものは素直に点数を入れる」というタイプ。
審査員のタイプ ②-②ウケ重視-客(構成重視)型
例:中川家の礼二さん、サンド富沢さん
「はじめの方のウケ方がMAXになっちゃって、それ以降にもっと強いのが来なかった、爆発仕切らなかった」
「ずっと安定して面白いけど、後半のたたみかけが欲しかった」
のコメントに代表される考え方
全審査員の方がコメントしていることではあるのですが、特にそういったコメントをすることが多いように感じる方を上記に挙げました。
これは同じようなウケ方であっても、右肩上がりにウケが増大していくような構成を重視する視点であり、お客さんが漫才を見終えた時の充足感(満足感)も重視しているような視点。
知名度の高い大会でありながらも芸歴制限がかかっていることで、お笑いに詳しくない人が新しいコンビやトリオを目にすることが多いM1において、如何に他と差を付けながら自分たちのインパクトを残せる漫才であるかという視点での評価とも言えるようなタイプかなと。
実際にはタイプ分けではない(改めて)
上記では実際の審査員の名前と共にこういうタイプ、みたいな言及の仕方をしていますが、実際にはレーダーチャート的にどの要素の意識がどれだけ強いか弱いかというものであり、どれか一つだけを持っているわけでも持っている持っていないのゼロイチでもありません。
ただ、この人はこの要素が一番強く出ていそうという話だったり、こういう審査フィルターが存在していることの説明として、一旦特定の審査員の名前と共に紹介しただけですので、改めてになりますがその点はご留意いただきますようお願いいたします。
採点基準を考える
前項目で挙げたものは、審査をする上での微調整ためのフィルター、もっと言えば無理やり優劣をつけるための評価基準であって、根幹的な部分にある評価基準ではありません。
じゃあその根幹的な評価基準は何かといえば、やっぱりそれは一般視聴者と同じ”面白さ”なわけですよね。
そしてそれは最近であればあるほど、スタジオの笑い声の単純なボリューム(音圧)がそのまま得点に繋がっている印象があるのですが、そのボリューム(音圧)が得点に直結していないようにも見える時も珍しくはありません。
それは、審査員にとっての”面白さ”が色々な条件によって変動するものであるからで、ここが視聴者からは見えない要素としてかなり含まれているわけです。
審査員は、普段からお笑いの世界で生きている
初めて美味しいお肉を食べたり、お寿司を食べたりした時の衝撃や感動は凄まじいものがあります。
しかし、2回目ではその1回目の感動を超えることはなく、30回や40回も食べていれば衝撃や感動というよりは安心や幸福といった別の感情に変わっているはずで、そこの特別感はどんどん減っていくでしょう。
これがお笑いでも同じだと思っていて、芸人さん達は横の繋がりも強く、人間関係上でも同じ芸人仲間と関わることが多いように見えます。
となれば、”面白さ”に触れている時間も一般人よりもはるかに長く、また多様な”面白さ”に触れていて、何なら自らその”面白さ”を生み出すことさえできてしまう。
だから芸人さん達というのは、一般人が”面白さ”の衝撃や感動を受けるものに対しても、もう慣れてしまっていると考えることもできるでしょう。
他と同じくらいウケていたのに、他と同じくらい面白いと思ったのに、何故か点数があまり高くついていないと感じる時は、大雑把に言えばだいたいこれが原因のように思っています。
もっと言えば、お笑いのプロでもある審査員が見た時に
”自分たちでも同じようなネタが簡単に作れるな”
”自分たちの方が面白くできるな”
と思ってしまうようなネタであると、ウケていたとしても”優劣をつけなくてはいけない審査”である都合上、そこが他の組より点数を下げていい理由になってしまって、スタジオでのウケ(テレビを見てて聞こえてくる笑い声の大きさや音圧)と点数が直結しないという現象が発生するのかなと思いますね。
また逆に、一般人の感じる”面白さ”以上に、芸人に衝撃や感動を与えている事象も存在するとも言えると思います。
”同じようなネタを書いてみたい”
”予想できない視点や切り口からのボケや展開で一本取られた感がある”
”真似したくても自分にはできない”
というような、芸人から見ても羨ましい・あっぱれ・悔しいという感情が湧くような漫才、更にそんな感情を超えてまでゲラゲラ笑わせてくれるような漫才に高得点が付いているような印象です。
分かりやすいところで言えば、一つはミルクボーイのネタ。
いわゆるシステム漫才と言われるような特定のパターンを繰り返すような漫才でありながらも、そのシステム漫才での展開に留まらず、一つの題材に対してややdisを含みながらの意表を突くようなあるあるを列挙していくという素人からプロにまで親しみ易いフォーマットまで提示したという点において、その面白さのみならず「その手があったか!」と芸人すらも唸らせるような点において高く評価されたのだと思います。
また同様に霜降り明星も同じで、ある種のシステム漫才的。
せいやさんが一人コントでボケをして、粗品さんがそれを解明するかのようなツッコミをするという構造によって漫才が展開していき、粗品さんはそのコントに入るわけでも止めるわけでもなくただの傍観者のまま終わる。
せいやさんを使った粗品さんのフリップ芸的でもあるという構造で、そのシステムも斬新でありながら一つ一つの大喜利的ボケが強いという点で高評価を受けていたのだと思います。
また別のところで言えば、ウエストランドやとろサーモンなんかは、単純なネタの面白さのみならず、そのネタをやるならばその人たちでないとここまで面白くはならないというような唯一性(キャラクター性)的な部分において、ある種の羨ましさや悔しさが存在しているという形の高評価な気がします。
上記をまとめていえば、”面白さに加えて、芸人にも刺さるもうワンパンチが欲しい”というのが審査員であるお笑いのプロの視点であるのではないか、というところです。
観客の存在
かつてのTHE MANZAIにおける視聴者票の入ったコンビと実際に勝ち上がったコンビが違うケースが56%以上であり、視聴者視点の感覚は審査と直結しないのは前述した通りです。
しかしながら視聴者の視点が審査に全く影響しないかといえば、それも違う。
というのも、事情は分からないですが、特に最近は”ウケの絶対量”がそのまま得点に繋がるケースが増えてきていると感じることが多いです。
審査員の若返り的な要素が大きいのか、視聴者の不満をある程度汲んでくれようとしてくれている方が多くなったのか、観客のウケが審査員から分かりやすくなったのか、考えられる要素はいくつかあるものの決定的な理由は分かりませんが、確実にウケ方の音圧が高いのに低い点が付くというケースは少なくなったと感じます。
となれば、近代のM1においてはそのウケの量から審査の結果が推測しやすく、その審査に影響を及ぼしていそうな”ウケ”を作り出しているのは一般応募で観覧に来ているお客さんということになるので、そこには視聴者の評価も”どれだけ笑えたのか”という素直な形で反映されていると言えるでしょう。
また、右肩上がりのネタが求められるのも、その視聴者の視点にもあります。
M1という大会は優劣が付けられて優勝者が決まるという性質上、
「どれだけ面白い漫才が見れるのかワクワクドキドキ」
というのに留まらず、
「誰が優勝するんだろう」
「誰が一番面白いのかを見極めよう」
というような気持ちで見ることが少なくないはずです。
となると、審査される側でも大会に関わっているわけでもないはずの視聴者の立場にも”緊張感”が生まれます。
ウケが取れない時間、いわゆるフリの時間が長く続くと「これで大丈夫なのか、点数が付かないんじゃないか」のような要らない心配をし出してしまい、お客さんが過緊張状態になるせいで、そのフリを落とすところでウケにくくなる。
これが芸人さんたちが良く口にしている”M1の空気”であり、M1ではウケないネタというのが発生してしまう原因なのではないかと。(だって何千組から選ばれた10組が面白くないわけはないはずなので、スベってしまっているように見えるものはだいたいこれが原因なんだと思っています)
だからこそ右肩上がりに笑いを爆発させていくことがお客さんを過緊張の状態に戻すことなく駆け抜けることに繋がり、それがウケにも繋がるし見終わった後のインパクトや満足感にも繋がり、審査員も高得点をつけやすくなるのではないかというのが自分の推測だったりします。
審査員はお笑いのプロである前に、同じ人間である
また、M1でよく言われる”出順によって優劣が付いてしまう問題”も視聴者の視点であるところは大きそうです。
というのも、
かなり面白くてウケていた組の直後はどうしてもそことの比較をしてしまったり、
逆に笑いきれない組が続いた後の爆発は反動分が乗っかってさらに大きくなったり、
前の組と同じような形式だとなんとなく飽きてしまったり、
お客さんのウケが、そのネタの持つ面白さからのブレ幅は大きそうであると感じることが多々あります。
(後から改めて見返したら、イメージしてたよりもずっと面白くて、なんでこれくらいしかウケでないんだろう?って思うことはかなり多いです)
となれば、最近であればあるほどウケの量が得点に影響してきている現状においては、出順の影響はかなり大きいと言え、それを生み出しているのは視聴者の視点(お客さん)であると言えます。
また同じことは審査員たちにも言えます。
審査員だって同じ人間ですから、甘いものをたくさん食べた後のショートケーキと、しょっぱいものをたくさん食べた後のショートケーキではその評価は絶対的に変わってしまうのは仕方のないことで、そこに更に会場におけるお客さんのウケという部分まで乗っかってきているわけですから、出順による影響というのが発生するのだと思います。
つまり、お客さんの過緊張気味の状況と、審査員がそれにやや影響を受けるというのもあって、(最近は特に)視聴者の視点はある程度織り込まれていると言えるわけです。
何と言っても漫才は生モノである
そして忘れてはいけないのは、漫才というのはそもそも舞台のものであって、目の前で行われたものに対する評価をしているのがM1です。
ところどころにCMが入って気軽にトイレに行けたりSNSを見るなどの行為を気楽に挟みながら一つ一つ気持ちをリセットしながら見れるテレビで見るM1と、現地でずっと緊張感を持ちながら見るM1とではある程度乖離があることも理解しなければなりません。
テレビで見るネタと、現地で見るネタとは、厳密には違うものだということです。
また、現地では途切れることのない一続きの大会であるからこそ、ネタを披露する前後の組の影響も強く関わってくるとも言えそうです。
M1は地続きのストーリーも存在している
また今までに言及してきたものとは別に、M1という地続きのストーリーも存在しています。
わかりやすいところで言えば、2020年の王者マヂカルラブリー。
2017年で上沼恵美子さんに冷たくあしらわれるような審査コメントと共に決勝最下位を取ってしまったマヂカルラブリーでしたが、2018年2019年と2年連続で敗者復活戦を敗北するも、その際に上沼恵美子さんへのメッセージを野田クリスタルさんが叫んでいました。
そしてついに迎えた2020年、土下座の姿勢でせり上がってきた野田クリスタルでひと盛り上がり。
音楽と共に階段を降りてきて始まった漫才の第一声は
「どうしても、笑わせたい人がいる男です」
というもので、会場が一気に湧きました。
2020年で初めてM1を見た人には一切伝わらないわけですから、これは明確に”M1”というストーリーを使ったツカミであり、それに反応して湧いたお客さんもそのストーリーに乗っかっていると言えるでしょう。
この、ある種反則技的なツカミが直接審査に大きな影響を及ぼすことはないのでしょうが、お客さんの空気を掴むのにはこれ以上ない効果があるはずで、前述した通りそのお客さんの視点は審査に影響を及ぼすわけです。
こうしたM1というストーリー上がもたらす効果は他にもあります。
分かりやすいところで言えば、オズワルド。
初めて決勝に上がってきた時には、静の漫才でありながらも一つ一つにパワーがあるハードパンチャーという斬新さを評価されていたはずなのに、今ではもうM1の王道のような扱いになっていて、期待値がかなり高いところに存在してしまっていて、なかなか点数的には弾けきっていないように見えます。
またモグライダーも分かりやすいですね。
2021年で初の決勝進出ながらもトップバッターを引き、トップバッター史上最高得点を叩き出したモグライダーでしたが、2023年で再度決勝に戻ってきた際にはその時と比較しての物足りなさから点数が伸び切らなかったというようなコメントを審査員がしていた記憶があります。
一つ一つをそれぞれで評価するのではなく、視聴者も審査員も”今までの決勝でのネタ”というものも乗っかった状態でリアクションをするのがM1というコンテンツであり、そこは大いに考慮にいれる必要があると言えるでしょう。
キングオブコントとは違う最終決戦方式から来る、審査方法の微妙な違い
またM1における優勝者を決める最後の最後である、最終決戦の審査方式は、同じ賞レースのキングオブコントとは微妙に異なるものとなっています。
キングオブコントは1本目と2本目の点数を合算しての合計点が高い組が優勝となりますが、
M1は審査員が一番良かったと思う組に投票をする形で優勝が決まります。
つまり、M1における2本目は、”点数が高いネタ”というのに留まらず”票を入れたくなるようなネタ”であることが大切であり、逆に絶対的に面白い残った3組の中で票を入れない理由があるネタだと入れづらくなるということでもあるわけです。
上記を踏まえたM1の見方
ということで、以上を踏まえたM1の審査を理解するための見方の大まかな方針は
- 基本的にはウケと得点は直結していて、そのウケは視聴者的視点であるから一般の感覚も審査の中にある程度は織り込まれている
- ただウケている中でも差をつけないといけないので、その差になる部分は芸人から見た時に「羨ましさ・あっぱれさ・悔しさ」というようなものがあるものの方が点が高くなりやすい(新しさと表現されることがあるものがだいたいこれ)
- その中でも審査員ごとに重視しているポイントや、そのポイントごとに強弱がある(漫才(師)のあり方・ウケそのもの・ウケ方など)
- そのウケには、M1という大会そのものに乗っかっているストーリーも含まれていることを考慮に入れる必要がある
- 最終決戦は”票を入れない理由をつけやすいネタ”には票が入りづらい
というものになります。
この観点で見ることで、およそM1の順位の目安になる気がしますし、納得感も上がるはずです。(自分はこういう視点で見ていて、まだまだ見つけられていない視点も一緒に探すように見ています)
2024のM1を見てみる
ということで、上記の視点でもって2024年のM1を軽く振り返っていきたいと思います。
トップバッターの令和ロマン
昨年不利だと言われていたトップバッターでの優勝を達成した令和ロマンが引いたのはまたしてもトップバッターで、会場がどよめき立ちます。
「またかよ!」って怒って出てくるのかな?
「またですか・・・」と落ち込みながら出てくるのかな?
「デジャブですね」と特に気にすることもなく出てくるのかな?
なんて色々ドキドキしながら待っている状況の中、ステージに上がった令和ロマンの第一声は
「終わらせましょう」
というものでした。
これがくるまさんが前々から名言してた”ヒール役”としての振る舞いというか、みんなが「そうだ、こいつらは昨年のチャンピオンであり、ラスボスなんだ」というのを思い出すと同時に、圧倒的なチャンピオンの誕生も願った瞬間だったりするのではないかなと思うんです。
今年のM1は、このラスボスを誰が倒すのか、もしくはこのヒール気取りの主人公が真の主人公に成り上がるのかというストーリーを一発でみんなの中に走らせ、王者として圧巻であり安定した場を掌握するかのような素晴らしい漫才を披露し、いきなりの高得点で暫定ボックスの1位席に居座るところから2024年のM1が始まりました。
ヤーレンズ
そして2番目のヤーレンズ。
前年のM1では令和ロマンに1票差で惜しくも敗れて準優勝となったヤーレンズには、あのラスボスを倒すだけの実力が確定しているという点で全組最大の期待がかかってたといえるでしょう。
その期待は、やや”流石に連覇はない”とも思われていた令和ロマン以上だったかもしれない。
しかし、いや、だからなのか、直前に王者として圧巻の漫才を見せられた直後であり、その最大の期待が満ちた空気の中で行ったヤーレンズの漫才は、そこまで爆発しきれませんでした。
そしてついた点数は令和ロマンから25点も離れた点数。
正直この点数ほどヤーレンズの漫才が物足りなかったわけではないと思うです。
だけど今回のM1は、”誰があのラスボスを倒すのか”というストーリーがみんなの中に走ってしまっています。
そんな中で順番がそのラスボス直後であったことから、ある種直接対決的な見え方となってしまったことで、昨年1票差にまで追い詰めることができていたヤーレンズへの期待は大きくなりすぎていたんじゃないかと。
その期待を要望を満たせるものなんて、きっと最初から存在しなかったレベルにまで。
だから、ありもしないはずの”最高”に届いていなかったことに対する落胆のような感情、”これでは令和ロマンに勝てない”という必要以上のマイナスイメージが発生してしまったことで、ヤーレンズはラスボス討伐隊には入れなかったというのが今回の見方なのかなと。
理不尽に見えるかもしれませんが、少なくともお客さんからはそう見えてしまっていて、それがウケに反映されて、それが審査にも影響される。
これがM1であり、見ている分には面白いところなんですよね。(芸人さんからしたら溜まったもんじゃないんだろうけど・・・)
真空ジェシカ
そんな落胆の直後、これまた決勝常連の真空ジェシカがやってきました。
しかも「ポップなしゃべくりの令和ロマン」「ポップな漫才コントのヤーレンズ」というポップ続きの後の、「一問一答型のハードパンチな漫才コントの真空ジェシカ」という、タイプの違う漫才。
決勝常連ということもあってその面白さは間違いないのですがそれだけではなく、ラスボスの令和ロマンの1本目とは違うタイプの漫才でもあり、ヤーレンズへの落胆によって希望を一つ失った後の真空ジェシカは、オーディエンスにとってはさらに希望の星に見えたのではないかなと。
点数も令和ロマンにあと1点と迫る点数であり、ラスボス討伐隊の資格ありという反応だったのかなと。
バッテリィズ
そしてその後の4組目からしばらくは面白いながらも弾けきらないもどかしい時間帯が続きました。
令和ロマンは場を掌握してホームにした上で漫才をするのに長けているから、きっと弾け切らないなんてことはない。
だから、多少の圧の中でも弾け切る漫才師を待ち望んでいた。
そんなもどかしい時間を終わらせたのがバッテリィズでした。
ある意味古典的とも言える”バカ(アホ)系の漫才”でありながらも、面白さを取り出す切り口は斬新で予想がつかない。
そして、正直このコンビの会場でのウケ量は他のコンビ達とはそこまで大きな差はなかったように思うのですが、点数は令和ロマンを11点と大きく超えるものがつきました。
恐らくこれは、審査員がラスボスキラーとして決勝に送り込みたかったというような意図もあったんじゃないかと思うんです。
当然前述したような、芸人が唸る切り口や展開というのは審査コメントでも言われていた通りなのですが、”ラスボスを倒す大会”という視点で見たとき、計算ずくで漫才を組み立てることのできる技巧派の令和ロマンを倒すなら、その反対とも言える人間味のパワーなのではないかという審査員の目論見。
これによって、”ポップな技巧派令和ロマン”というラスボス討伐に向けて、”一つ一つがハードパンチな真空ジェシカ”と”人で魅せるバッテリィズ”が選ばれたという構図になったわけです。
エバース
今回、ヤーレンズと同様に「令和ロマンというラスボスを倒すストーリー」の犠牲者とも言えるのがこのエバースというコンビ。
正直例年ならば決勝進出して、そのまま優勝をしてもおかしくないほど面白かったと思います。
しかしながら、今年走っていたストーリーは、打倒令和ロマン。
それに加えて、そろそろ誰が最終決戦にいくのかの算段が立ってしまう9組目というタイミングも不運だった。
9組目の出番を控える時点で令和ロマンは2位。
仮にこのエバースに高得点を付けてしまうと、残っているのは、どうなるか分からないトム・ブラウンというのもあった。
最初からうっすら漂っていたものながら、もうこの時には令和ロマンを最終決戦に残したいという空気が決定的になってしまっていたはずなんですよね。
それに加えて、エバースは”話の展開で魅せる技巧派”という見え方なので、”人で魅せるバッテリィズ”の後だと、ラスボス討伐隊にはややパンチ不足に見えてしまう。
そんな中でも真空ジェシカにあと1点と迫るほどの高得点ですから、正直とんでもないと思います。
来年以降、絶対また決勝で見ることになるコンビだと思うので、名前を覚えておきましょう。
最終決戦
そして迎えた最終決戦。
ネタ順は3位→2位→1位という例年通りの感じで、真空ジェシカ→令和ロマン→バッテリィズ。
当然3組とも面白かったですが、一番ウケていたのは令和ロマンだったかなと思います。
後日の出演していた番組でも「令和ロマンはとても受けていたので、負けたと思った」とバッテリィズの方々がコメントしていたので、その感覚はそこまで違ってはいないのかなと。
そして最終決戦は前述した通り”票を入れたくなること”と”票を入れない理由がないこと”が大切です。
またこれが、前述もした審査員のタイプ分けが関わってきます。
漫才(師)のあり方重視 の審査員
前述した通り、これは「M1に提出された漫才(師)という作品」としての評価をするタイプです。
つまり、「M1という賞レースにおいて、どれだけ自分たちのオリジナリティを出しながらも面白いものが作れたか」という視点で見るため、真空ジェシカの2本目のような”他人の名前や作品(歌を含む)を使って笑いを取る”という点をやや好まない傾向にあるかなと。
そしてここには博多華丸・大吉の大吉さんとノンスタ石田さんとアンタッチャブルの柴田さんにこの傾向が強めに見られそうだと思っています。(この3人は最終決戦令和ロマンに投票しています)
実際1本目は真空ジェシカに一番高い点をつけた大吉さんも最終決戦では令和ロマンに入れているのですが、これはかまいたち山内さんも同様なので、もしかしたら山内さんもこのタイプなのかもしれません。
また”M1という大会”というものを強く意識しているとも言えるタイプですので、M1そのものの2本目を見ての決選投票システムを意識し、1本目との合算的な思考もありながらもが2本目での差が大きい場合は乗り換えるということをしやすい審査員なのかなと。(今回だと1stステージで最高点をバッテリィズや真空ジェシカにつけたのに、最終決戦では令和ロマンに投票したのは大吉さん、石田さん、柴田さん、山内さんの4人ですが、そもそも付けていた点数も僅差だったので2本目と合わせてひっくり返っただけかもしれません)
| 大吉 | 塙 | 哲夫 | 若林 | 石田 | 山内 | 柴田 | ともこ | 礼二 | ||
| 令和ロマン | 96 | 93 | 90 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | 93 | |
| ヤーレンズ | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 94 | 90 | |
| 真空ジェシカ | 97 | 94 | 90 | 93 | 95 | 97 | 94 | 95 | 94 | |
| マユリカ | 93 | 91 | 88 | 91 | 91 | 90 | 89 | 96 | 91 | |
| ダイタク | 90 | 93 | 89 | 92 | 90 | 92 | 88 | 94 | 92 | |
| ジョックロック | 89 | 91 | 91 | 90 | 89 | 93 | 88 | 95 | 93 | |
| バッテリィズ | 95 | 93 | 95 | 95 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | |
| ママタルト | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 93 | 89 | 92 | 93 | |
| エバース | 94 | 94 | 93 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 | 96 | |
| トム・ブラウン | 95 | 95 | 92 | 93 | 88 | 90 | 87 | 94 | 89 |
圧倒的だったミルクボーイと、連覇で圧倒性を見せた令和ロマンの違い
今回連覇という圧倒的な結果を出した令和ロマンですが、過去のM1において圧倒的というと、歴代最高得点を叩き出したミルクボーイが思い出されます。
あの年は、UFJのネタを引っ提げたかまいたちですら刃が立たないミルクボーイというとんでもない圧倒的っぷりを見せていて、まさしく他の組を圧倒的なパワーでもって上から叩き潰したようなM1でした。
じゃあ連覇を達成した令和ロマンがそういう勝ち方をしたかと言われると、正直そういうイメージはないです。
とても達者ではあるが、他の組が霞んで見えるほどのパワーを感じるほどではなかったと思います。
しかし令和ロマンは実際に連覇という前人未到の大偉業を成し遂げたわけなので、何かしらの圧倒的さを持っていたはず。
それは一体なんなのかといえば、場を掌握する力なのではないかというのが自分の見方です。
2023年のトップバッターでの優勝から見えていたその力
2023年のM1でトップバッターとしてやったネタは、冒頭でケムリさんの「ヒゲともみあげが繋がっているのはなぜか」ところをお客さんに問いかけて考えさせるような間を作ってスカすという流れをツカミとし、その話題だけで30秒近く使っています。
M1のネタ時間は4分とされているので、ケムリさんの顔面だけで1/16の時間を使っている計算です。
さらにそこからネタの本題に入るかと思いきや「そんな松井ケムリさん率いる皆さんに……」と、更にお客さんに向けたボケを入れ、さらにここで12秒ほど使っています。
そしてその後、ようやくネタの本題に入ってこれからの話題を提示し、そこで「それをマジで今日全員で考えたくて」と言いながら座り込んでお客さんとの物理的距離を縮めるという、ここでもお客さんへの働きかけを行っています。
なんとここまで1分30秒。
この1分30秒の中で、お客さんと令和ロマンが仲間であるかのような空気が醸造され、それ以後もくるまさんは定期的に「緩やかに曲がりません?」「日体大って可能性ない?」「話戻しますね」「ちょっ、見て…!」というのをお客さんの方に顔や目線を投げかけるように語っていて、途中もくるまさんがお客さんに「そう」というリアクションをしていたりします。
M1決勝初進出で、出てきた時は初めて見るコンビであろう中、この1分30秒で令和ロマンの仲間となってしまい、ずっと自分たちの方を気にかけてくれる漫才を1本目に見てしまったのが、このM1だったわけです。
令和ロマンのお客さんにも都度都度で語りかけてくれるような”自分たちも参加しているかのような漫才”を見たあとでは、その後の漫才は”見ているだけの漫才”になってしまう。
そっちが普通だったはずなのに。
こうしてお客さんやその空気を掌握した令和ロマンの次にネタを披露したシシガシラは、ボケとツッコミだけの会話で物語が展開していったことが災いしてか、結果9位に終わってしまっていたりもします。
今見ると、もっと得点がついてもいいくらい面白いんですけどね・・・
そしてトップバッターからの最終決戦に出てきた令和ロマンは、「お久しぶりですね」と早速お客さんに語りかけ、再び「覚えてますかね、松井ケムリ君。」という語り出しから再び同じようにヒゲともみあげの話をし、1stステージ時とは違う解答でスカすというツカミをしています。
その後の余韻ボケ的な「顔でもんじゃ作ってるわけじゃないの?」というのをかました際も、お客さんの方に目線を向けて語りかけるように動いていたりします。
ここまでなんと約40秒。たっぷり時間を使ったツカミ。
その後漫才コントに入っていくのですが、その入りも、直前までお客さんに「今から人力でダイジェスト版やるんで」と語りかけ、最後に見ている人の代弁者であるツッコミ(ケムリさん)に「ちょっと指くわえて見てて」と話しかけることでコントに入る。
ツッコミのケムリさんがこちらに強く語りかけて来ることはないのですが、それはケムリさんが我々見ている側の代弁者的ポジションであるから。(そもそもツッコミとはそういう役割がちですし)
だからくるまさんはずっとお客さんに語りかけていて、話の進行上のポイントでのみケムリさんにだけ話を振るという構造を取っていて、常にお客さんに開かれているようなオープンな漫才なんですよね。
対して最終決戦2組目のヤーレンズは、令和ロマンがじんわりと支配している空気の中、コント漫才という閉じた漫才で戦った。
さや香は開かれてはいたけど、参加する漫才というよりは参加させられる漫才のような形で散った。
そして結果が、トップバッターから空気を支配し続けていた令和ロマンの優勝だったわけです。
じゃあ2024はどうなんだ、そんな長い時間のツカミなんてなかったぞ!!という話になるはずですが、それは違います。
前述した通り、M1にはM1という一本のストーリーが走り続けています。
令和ロマンの今年ツカミは、去年の優勝というのでもう終わっているんです。
だから連覇を取りに来た今年の令和ロマンのツカミは、「終わらせよう」の一言で十分だった。
そうしたツカミ一発で、
”今大会は、誰が令和ロマンを倒すのか”
”このヒール気取りの主人公が真の主人公に成り上がるのか”
というストーリーを会場やM1そのものに走らせ、今大会の主役を自分たちにしてしまった。
案の定その次のヤーレンズでは”力不足”とされてしまって、本来の面白さよりも低い点がついてしまったような状況になり、ライバルを一人蹴落とすことに成功するわけです。
また、そんな”主役に転じる”という視点は、2本目の漫才コント内でケムリさんが覚醒するクライマックスシーンでも描かれており、まさしくあのシーンでは令和ロマンが主役に見え、なんなら後光が差しているようにすら見えました。
そしてその後にネタを披露したバッテリィズは、そんな令和ロマンの空気の上で二人の会話のみで進んでいく閉じた漫才を披露したことで、そこまで爆発し切らなかった。
(ただ令和ロマンを3番目にしていたらしていたで、ケムリさんの覚醒シーンがまんまその後のM1優勝をイメージさせてしまったと思うので、そこら辺がくるまさんの計算高さという感じもあります。空気の掌握のみならず、策略家でもあるところが強すぎますね。)
令和ロマンの圧倒的強みは、見ている側が令和ロマンそのものにされてしまっているような錯覚すら覚えるほどの、お客さんや会場の空気の掌握力。
テレビで見ていてこれなので、現場ではもっとすごいのでしょう。
つまり令和ロマンは、直後のコンビに強烈なデバフを与え、その後もずっとほんのりと弱体化を与え続ける持続カードみたいなもの。
だから令和ロマンが輝くのは、その持続カードの発動時間が最も長くなるトップバッターであり、それを2年連続引いているというところが、やっぱり持っているということなのかな、と思ったところでもありました。(とはいえ、まあ一番最後だとさすがにあれだけど、普通に5~7番目に出ていてたらもっと令和ロマンは弾けてたとは思いますw)
ごちゃごちゃ語っていますが、令和ロマンはすげーぞということです、本当におめでとうございます。
M1はまた一つ終わった
M1の歴代最高得点を叩き出したミルクボーイの圧倒的優勝により、ある意味でM1というのは一つの終わりを迎えたというのが自分の見方だったりします。
事実、その後の2年はキャラクター性の強い漫才(マヂラブと錦鯉)が優勝しており、新味を求めたようなところもあるのではないかなと。
少なくとも後に出てきたくらげやカベポスターや東京ホテイソンのようなシステム漫才的であるものの点数が軒並み低調で、ミルクボーイがシステム漫才の最高を叩き出してしまったが故の事象なのではないかと思ったりするところです。
また2022年のウエストランドも”あるなしクイズ”という形式を取ったシステム漫才ではあるものの、そこには井口さんの人間味が見える面白さが存在していて、”システム漫才×人”という結局は人のパワーが大きいのが2022年の結果だという解釈です。
そして今回の令和ロマンの連覇は、ミルクボーイと同様に”一つの終わり”を作ってしまったのではないかと思っています。
それは”閉じた漫才”の終わり。
あまりにナマ感の強い令和ロマンの漫才は、以後の閉じられた漫才、作り物臭さが見えてしまう漫才を終わらしてしまったのではないかという疑惑もありますが、それは来年以降のM1で確かめることにします。
個人的2024M1点数
個人的なM1の見方は”誰が優勝にふさわしいか”という見方ではなく、審査員の出す結果をおよそ推測できるような状態を目指すというものであり、そういう”お笑いが分かる”状態を目標としていたりします。
だから自分が出ていたコンビに優劣を付けるというのは烏滸がましいのでしませんが、優劣ではなく個人的な好みの順位なら付けてもいいはずなので、それだけ最後に少し語ろうかなと。
個人的1位 令和ロマン
良さは散々上で語ったので、省略。
正直圧倒的な存在というのはどの分野においても盛り上がるもので、お笑いの中でもそんな分かりやすい形の圧倒的な存在がいてもいいはずだと思っていたので、なんだかこれからがワクワクします。
3連覇は目指さないと言っていたけれど、いつか出るかもしれないことを仄めかしてもいる。
今後の令和ロマンがちょっと楽しみすぎますね。
個人的2位 エバース
今大会で一番知れて嬉しかったコンビがこのコンビ。
正直言えば敗者復活で見たことはあったのですが、その時のイメージの何倍も面白かったなという印象で、来年以降の優勝があり得る気がしているコンビです。(オズワルドのように凄まじい実力者と認められながらも優勝まで手が届かない存在になってしまいそうな空気もありますが、なんとかなって欲しいです)
初めて見た時から次以降のM1に期待したい!と過去に思ったコンビが、「オズワルド」「真空ジェシカ」「ウエストランド」「錦鯉」「もも」「モグライダー」あたりだったりするので、自分の見る目が確かならエバースもまた決勝で見れる日が来るんじゃないかと本当に楽しみです。
個人的3位 トム・ブラウン
正直優勝はないだろうなと思いつつ、すごく応援していたコンビです。
ずっと何やってるか分からないのに、何故かずっと面白いネタは、理屈じゃない凄さを感じますww(からあげ4とか見せ算も大好きなので、ある程度同じジャンルだと思ってますねw)
ネタ終わりのみちおさんの頭が真っ赤だったのかすごく印象的で、すごく気持ちが入っていたことが分かるような感じで悔しさが伝わってくるようですが、あのスタイルでM1を戦い抜いたトム・ブラウンはすごくカッコよかったと思います。
個人的4位 真空ジェシカ
4年連続決勝というとんでもない実力者でありながら、今大会で初めて最終決戦に残ったらしく、とても意外でした。
1本目のネタは真空ジェシカらしい切り口でありながらも、分かりやすさと綺麗さのまとまったM1っぽいネタで、これは今年優勝もあるか!?と思っていたら、あの狂気の2本目が・・・www
個人的にはめちゃくちゃ腹抱えて笑いましたし、大好きなネタですが、ああいうのでは優勝させてもらえないだろうな・・・と思ったら、面白さに素直な塙さん以外の票はなく、やっぱりなと・・・www
その塙さんにも「今からでも令和ロマン変えて…」と言われてしまう始末で、真空ジェシカらしいっちゃらしいですが、個人的にはすごく好きなコンビですし、その実力は間違いないのでいつか優勝する姿も見れたらいいなと思います。
個人的5位 ジョックロック
実はエバースと共に今後のM1で楽しみにしたいコンビです。
点数こそ伸びなかったものの、会場のウケは他コンビとさほど差があったようには思えませんしちゃんと面白いものだったと思いますが、プロの芸人さんから見れば、ある程度作り方から発想から展開のさせ方から、真似できてしまいそうというようなネタだったことで点数が低く付いたのかなという印象でした。
間のとり方やテンポ、ユーモアの方向性、結構全部好みの感じで、また決勝で見ることができたら嬉しいなと思いますね。
個人的6位 バッテリィズ
このコンビも敗者復活で見たことがあったのをなんとなく覚えていて、ボケもその時と同じものがいくつか見受けられ、初見としての感動がない分ちょっと印象には残りづらかったです。
また2本目の「大仙公園」からの「鍵穴みたいな…」というので、仁徳天皇陵古墳を、M1の決勝の舞台であるテレビ朝日(東京)でイメージさせるのは少し難しかったのかなという印象を受けました。
自分はギリ気付けましたが、面白さが湧いてくるようなタイミングでは気付けなかったです。
同じように、あの場であのテンポ感では気付ききれない人は結構いたんじゃないかなと思います。
ここが活動場所が関西にある難しいところなのかなと思ったりもしたのですが、どうなんでしょう・・・。
手の内がバレてしまっての来年以降はちょっと難しそうな感じもしますが、オードリー的な匂いを感じるところでもあるので、今後の活躍を楽しみにしたいです。
個人的7位 ヤーレンズ
個人的には去年より今年の方が”分かりやすい”ネタになっていたかなと思います。
なんとなく自分は、”ここで笑って””はい次いくよ””の繰り返し的なネタが親しみやすいですし、よく見る形なので好みなのですが、去年のヤーレンズはその常識から外れた”ボケるけど分かる人だけ笑ってくれればいいよ”みたいな感じでズンズン進んでいくような、咀嚼しきれないまま次に進んでいってしまう感じで笑いきれなかった部分がありました。
対して今年はむしろその一般的な構造に寄っている印象を受け、個人的には好みでしたが、去年ヤーレンズが評価されていたポイントからは離れていってしまっていたようでもあるのかなと思っていたら、実際にコメントでも「もっとしょうもないのが見たかった」と言われていて、ああやっぱりそうなんだなと思った次第です。
M1上における令和ロマンの最大の被害者とも言えるこのヤーレンズですが、まだあと数回は出れるようなので、どこかでこの雪辱を果たす瞬間が見れるとドラマチックでいいなと思います。
個人的8位 ダイタク
双子コンビならではのネタという感じではありますが、その題材はヒーローインタビューというものだったからか、キングコングのネタを思い出したりもしました。
個人的にはそのキングコングのネタの方が面白いかなぁというイメージですね・・・(テンポよく軽快にボケを重ねていくのが好きだったりするので)
また、双子ではないのですが同じ兄弟コンビのミキを衣装からイメージをしてしまったりもして、展開力(飽きなさ)という面ではミキの方が圧倒的だなぁと思うと、正直物足りない印象でした。
その人柄や人間味的な部分が分かっている状態だったらもっと面白いネタだったのかなと思うのですが、M1初決勝だったところが災いしたような感じもあるのかなと。
ラストイヤーということで今後どこかで見れるかどうかは分からないのですが、どこかでまたダイタクの漫才が見れたらいいなと思います。
個人的9位・10位 ママタルト・マユリカ
本当に申し訳ないのですが、ツッコミが異常なハイトーンで、いかにも”ツッコんでます”という感じのツッコミは好きではありません・・・(ボケならおちゃらけに見えるのでいいんですけども・・・)
自然な会話のトーンからかけ離れすぎてて冷めてしまうんですよね・・・(昔の滝音とか東京ホテイソンも同じ理由で好みではなかった)
今後もあまり漫才が好きになることはなさそうですが、いわゆる平場と言われるようなバラエティでは面白かったシーンをいくつか見ているので、そういう場面で楽しめたらいいなと思います。

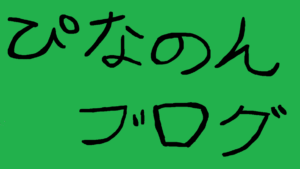
コメントお待ちしております!